|
�䕗�N���u
�ēF���ĐT��
���y�F�o�[�r�[�E�{�[�C�Y
�L���X�g�F�H���R�M�A�O��T��A���i�q�s�A�吼���ԁA�O�Y�F�a�A���c�_�A�����[etc.
�P�X�W�S�i�f�B���N�^�[�Y�E�J���p�j�[�j
�������䕗���������ĉƂɋA��Ȃ��Ȃ������w���O���[�v�́A���̖\���J�ɏ悶�Ċ����������B
���ĐT��炵�����ʼn����J�����̌������ɂ́A�p���c�꒚�łǂ���~��̒����A�܂��͑̈�ق̃X�e�[�W�ŔM�S�ɗx��܂��鏭�N����������B
����Œ��Q�V�������Ŋw�Z���T�{���ē������Ԃ���Ă��������i�H���R�M�j�̓i���p���Ă�����w���i�����Ƃ��̂�j�̉ƂɘA�ꍞ�܂��B
�v�t���̃C���C���Ƒ䕗�����肠�������̊Ԃ̉����B
�D���Ȏq�ɍD���Ƃ������i�����ōD���Ȃ̂��ǂ������킩��Ȃ��Ȃ��Ă�j�A�M�ɕ������ꂽ�悤�ɖ\�͂Ŕ���싅���̏��N�A�䕗�������āA���̊O�̂ǂ����悤���Ȃ��̂���Ƃ��������ɒ��ʂ��������ȏ��N��������s���́E�E�E�B�i���_�Ƃ̈ꑰ���v���o�����͖̂l�������낤���i�j�j�܂��A��̃V�[���A�ے��I�ȃV�[���������������Ėʔ����B
 �����Ȃ�O���ł��ꂳ��̕z�c�ɓ����ăI���j�[���n�߂�H���R�M��A�싅���̕�����Ƃ�ŏo����������肵�Ȃ���u�������܁B��������v�ƌJ��Ԃ����N�A�����đ�w���̉Ƃ��瓦���Ă����H���R�M���������̏��X�X�ŏo��A�I�J���i�𐁂���̃t���[�N�X�́u�I�J���i�͖鐁�����̂ł��v�ƂԂ₭�n���i�j�B�킯�킩�߁B �����Ȃ�O���ł��ꂳ��̕z�c�ɓ����ăI���j�[���n�߂�H���R�M��A�싅���̕�����Ƃ�ŏo����������肵�Ȃ���u�������܁B��������v�ƌJ��Ԃ����N�A�����đ�w���̉Ƃ��瓦���Ă����H���R�M���������̏��X�X�ŏo��A�I�J���i�𐁂���̃t���[�N�X�́u�I�J���i�͖鐁�����̂ł��v�ƂԂ₭�n���i�j�B�킯�킩�߁B
���Ȃ݂ɂ��̉f��ł̉��Z���]�����ꂽ�H���R�M�́A�W���E�W���[���b�V���́w�~�X�e���[�E�g���C���x�ɏo�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�v�t���̟T�ς�������̕s�����A�N�������Ƃ��̖����ꒃ�������������A���B
�r���ŗ��_�F���̉���B
'84�N�x�L�l�}�{��x�X�g�e����T�ʁA'85�N�x�������ۉf�惄���O�V�l�}����O�����v���B
���i���C��
|
����Z�b�N�X�֎~�� �F��喼
�ēF��ؑ���
�r�{�F��ؑ����E�|�D���T
�L���X�g�F���{�����A�T���h���E�W�����A���A���a�G�A�a�R�i�A�R��V��etc.
�P�X�V�Q�i���f�j
���������a�l���Z�b�N�X���|�ǁA���̂܂܂ł͂����p�������܂�Ȃ��Ƃ����ďł�ƘV�i�a�R�i�j�����B
�t���l�̏��B�ƈ��̖����ؐ��j����Ў�ɃG�����w�Ԃ��P�l�i���{�����j�Ƃ̏���ł͑��ۂ̉��ɍ��킹�Ăǂ�ǂ��ǂ�ƁA����Ă݂����̂̂��܂��������A���ɓ����đ����Ă����t�����X�̔��l�i�T���h���E�W�����A���j�Ɠ�̍��l�����̃e�N�j�b�N�Ő��̉��y�ɖڊo�߂����a�l�����Ƃ����낤�ɉ��y��Ɛ肵�悤�Ƃ��������炳����ρB
�܂�ŃW���C�A�����v���t�������̂悤��"�Z�b�N�X�֎~��"���{�s���ꂽ�̂ł���I
���������R�����Ȃ��̏�߁B����������~���s���ő卬���I���a�l������Ȃ̂��悻�ɂ��C�ɓ���̃T���h���Ɓu�Ɋy����`�v�Ƃ��܂����Ă钆�A�����̓s�[�N�ւƒB���A���Ɂu��点��`�I�v�ƈꝄ�u���B
�u���B�����Ă�肽����ڂ��[�I�v�Ƌ����Ɛb�����B
�����ĕP���ɖڂ̓G�ɂ���Ă����T���h���͕t���l�B�̃����`���A����ɉƐb�̂P�l�ƌ�����Ă��܂������Ƃ���A���a�l�̒m��Ȃ������ɏ�߂̋K��ʂ�A�C�ŋt�����ƂȂ��Ă��܂��B
���������a�l�͋֎~�߂����ւ��A���ɂ͂���Ƃ������삪�K��A�݂�Ȃ������炶�イ�Ō����n�߂�̂ł������Ƃ��B������B
�u�I���̑��ɃG�T���`�v�u�����������܂���`�v�Ƃ����悤�ɂ��̏��r��v�������ĉ����������Ƃ����i�R�j�ݒ薞�ڂ́A�n���G����y���㌀�B
��؊ē�����o�g�Ƃ����̂́A���P�߂������X�g�ȊO���o���������Ȃ����i�j�B
�����ǂ��菸�V���邨�a�l�ɍ����B�Ă��ǂЂ����B
���i���C��
�@
|
�E�l������
�ēF���{�씪
�r�{�F�R�蒉��
�L���X�g�F����B��i�j�[�M���j�A�V�{�p���i����{�l�����ߐR�c����j�A�c�ߎq �������D
�P�X�U�V�i����j
���������_�a���҂��E�l�҂Ɏd���ďグ�đ���{�l�����ߐR�c����i���̓i�`�X�̎c�}�ɍv�����邽�߂Ɏז��Ȑl�Ԃ�r�����Ă��鋶�M�I�c�́j�Ɩ����}�b�h��T�C�G���e�B�X�g�i�V�{�p���j�ƁA�ꌩ�S�R�_�������Ɍ�����n�R�ł����Ȃ���w�u�t�Ȃ�����̓v���̎E�����ł���j�[�i����B��j�����˂�����Ă����Ƃ�ł��Ȃ��f��i�j�B
���p���{�O�O�V�e�C�X�g�ɒɉ��Ȋ씪�߂���������O�㖢���̃A�i�[�L�[���ɉ��ȃu���b�N�E�A�N�V�����E�R���f�B���B
�B��鎩�q���̃X�p�C�������Łu������I�o�p�A������I�o�p�I�v�Ȃ���Ă���肵�Ă���A����ƓV�{�̐��_�a���ł̑Ό��V�[���̓o�b�N�̟B�̒��̗l�X�ȏǏ�̊���(�W�c�ŃX�N���b�g���Ă銳�҂Ƃ������肵��)���킹�Ă����B
�ׂ��ȃf�e�B�[���܂ŁA���䂢�Ƃ���Ɏ肪�s���͂��Ă��āA�ڂ������Ȃ��B
�P���|�����Ă���13�l�̎E���������͑S���L���K�C�����A���Ƀo���G�[�V�����L���i�j�B��炪�E�����E�j�[���A��x�j�炵�����������������Ǝv����U�^�[��������A�����ɃZ�R���B������|�ԈႢ�Ȃ��ł���B
���̎�̉f��Ɍ������Ȃ������̗�����������肠��B�Ƃ����̂��r�{���A���̃��p���O���⒆���N�ē̃M�����O�f��u�낢���ƂȂ�K�ɂȂ�v�Ȃǂ���|�����R�蒉���B
�ޓ��̏���Ă�Ԃ��{�胋�p���Ɠ����t�B�A�b�g�������肷��i�j�B
�f�撆����L�`���C���Č�����������̂��܂��ꋻ�i���j���ĂȂ���ōĔ��̗\�薳���I�Ԃ�͂͂́I�Ƃ����킯�ʼn��{�씪���㌀�̍ō����삪����B
�ςȂ���͟B�̒��ŃX�N���b�g�P�O�O�I
���i���C��
|
|
�]�ː에���S�W ���|��`�l��
�ēF�Έ�P�j
�r�{�F�|�D���T�i����F�]�ː에���j
�o���F�g�c�P�Y�A�y���F�A��؎��A�R���Ă�q�A�R���O ��
�P�X�U�X�N�i���f�j
�������Έ�P�j�������v�������]�ː에���̢�p�m���}����ݣ�A��l�Ԉ֎q��A��Ǔ��̋S��Ȃǂ����~�b�N�X�B�i������"�S�W"�Ƃ������Ă�̂�(��)�j����ɏ��X�̊�V��X�p�C�X�������č��グ���g���f���M��B
�܂��ɂ��ꂼ�A�J���g���̃J���g�ł���I�I
��҂̗��ł����l���͉��̂��ߋ��̋L�����������܂ܐ��_�a���ɂ����B������E�o���A���ƒ��̃T�[�J�X�c�̏��̎q�̂ƒm�荇���A�����̏o���̎肪����邪�ޏ��͎E����Ă��܂��B
�����ĕ���͂Ƃ���C�ӂ̑��ցB�����Ŏ����ɃE���t�^�c�̖��Ƃ̎�U�߂�����ł��邱�Ƃ�m�����ނ́B��������A���̂Ɠ���ւ��A��U�߂Ƃ��Đ����Ԃ�i���̎��̂܂ʂ��Ȃ��V���R���O�i�j�j�A����̉ߋ������ǂ�͂��߂�E�E�E�Ƃ����̂����������B
�����āA���̑��ɂ���Ǔ��Ɏ肪��������߂��ނ��������̂́A���܂�Ȃ��琅�~���̂���������A�X���e�p�̕��e�B
�����Ĕނ�������l�H�̊�`�l�Ԃ̃��[�g�s�A�������I�I�E�E�E���Ă��ꂪ�܂��|���Ȃ��̂Ȃ�́I�����������I�ȃ|�b�v�ȃC���[�W�̘A���ł���B
�y���F�̃L�b�J�C�ȓ�����M���ɁA�ނ����ۂɗ�����Í������c�̃V���[�^�C���ł��`��i�j�B
�j���S���̏������A�╲�h�肽����̐l�H�t���[�N�X�������x��|���̂��I�����Ė�����������������ƏX�j�̃V�����o�����i�Њ��ꂪ�ߓ����b(��)�j����l�����ؒf��p�I�����̕��Ɨ��ɗ������͂������ǎ��͔ޏ��͖��ŁE�E�E���ăX�g�[���[���Ȃm���I�ˑR����閾�q���ܘY�����̎肪������Ȃ��͂��Ȃ̂ɂ�����������I�ꌏ�����I�������������I�E�E�E�E���ď��Ă邤���Ɍ}����Ռ��̃��X�g�V�[���B�������������I�����Ȃ�j����`�����G�������B���������[��I�ƘA�Ă��Ȃ����юU��l�ԉԉ��ǂ�����ǂ�����ł��������V��f���ɂ̓_�u���V���[�b�N�I�_�u���V���[�b�N�I
����ɂ��Ă��Q�l�̐�����Ŕ��ł������͐�ɂ����������I�i���j
�M�҂��ς����R���u������ق͂��̃V�[���ł܂��Ɋϋq����ɁI�i�j��O���̃��X�g�V�[���͂Ƃɂ����K���I
���i���C��
�@
|
�ߏD����
�ēF��ؐ���
���āF������P�^�r�{�F��a����
�L���X�g�F���ؗt�q�A���c�F�Y�A���c�^���A�]�g�ǎq�A���ˏ� etc.
�P�X�V�V�i���|�j
�������w�E��������x�i'68�j��������Ƃ������R�œ�����ǂ��o����Ĉȗ���ؐ����ē����āF������P�A�r�{�F��a�����Ƃ������͂ȃT�|�[�g�āA��10�N�Ԃ�ɔ��\�����{��i�́A���Ղ̔��ؗt�q�̃R�X�v���V���[����]�g�ǎq�̃X�g�[�J�[���L�Ɖ����㔼�A�����ė���s�\�̃��X�g�܂ŁA��O���킵���s���ňُ�ȉ��o�Ɩ����̖��������ȓW�J�Ń��X�g�܂œ˂�����L���K�C���[�r�[�Ȃ̂ł������I�i�j
�E�E�E�Ƃ肠�����A�剉�̐V�l���D�̖��O��ǂ����ė~�����B���ؗt�q�E�E�E�����A���́u�������̃W���[�v�̔�����l�Ɠ��������Ȃ̂ł���I�ǁ[�Ȃ��Ă�́I��������I�i�j�E�E�E�ĂȂ킯�ŁA���炷�������Љ�B
�Ƃ���a�щ�Ђ��V�l�v���S���t�@�[�̍���ꂢ�q�i���ؗt�q�j��ꑮ���f���Ƃ��A�v���C���ɂ��낢��ȃt�@�b�V������g�ɓZ�킹�ă^�C�A�b�v���ʂ��v��o�����B�L���b�`�R�s�[��"���Ă̕��A�o�[�f�B�E�`�����X"�B�����đ傫�ȑ��ŗD�������߂��ޏ��͈��X�^�[�ƂȂ�A�����ߍx�ɍ��@���\���A��ƂQ�l�ŕ�炵�n�߂邪�A�ߏ��̃��W�E�}��w�łꂢ�q�t�@���̍]�g�ǎq�i�����I�j��瀂��������Ă��܂������Ƃ���b�͋}�]�B���̍]�g��w�͑��̉�����l�^�Ƀl�`�l�`�Ɣ����䂷��n�߂�̂ł������I
����ɕ����ɂ����肱�ނ�A����ł������̂ɑ䏊�łꂢ�q�̒�̂��т����o����A�ߏ��̎�w���ԋy�т��̉Ƒ����吨�Ă�ŗ��s�C�����������ς��߂��A��肽������̃L���K�C�I�o�^���A���ɕϐg�B�I���ɂ͂ꂢ�q�Ɏ����̕v�ƐQ��Ɨv������ȂǁA���ł����܂ŁH���Ăقǂ̖\���͎��ɕs�C�����`���I�i�j�E�E�E����Ŋ炩��̂ɂ����Đ^���ԂȐ��������A�S���t��ŃJ�����Ɍ������đ����Ă��錴�c�F�Y���Ӗ��s�������A��Ԃ������͎̂��͂ꂢ�q�̒�̏��N�ł���i�j�B
���̖̉��ł̓�̏����Ƃ̓�̉�b�����킷�V�[���������ɎU��߂��Ă䂫�A���X�g�ł͂����ނ�ɏe���Ԃ������ĉ�ʂ��ƏĂ��s�����Ƃ����劈��Ԃ�I�i�j�B
�����A�N�͂��ُ̈퐢�E�Ő��C��ۂ��Ƃ��ł��邩�H
���i���C��
�@
�@
|
�_��
�ēF�x��O��
�o���F���R�Y�O�A��u�����R�A�ݓc�X�A�X��V�A����A�X�ꐶ ��
�P�X�U�W�i����j
�������Â����͋C�������o�����Ƃ�����Ă͂�����ǁA����ς�ǂ����猩�Ă��參H�ȉ��R�Y�O���E�����ɕ�����A�{�i�n�[�h�{�C���h���́B
�Ƃ��낪���̉f��̊ςǂ���͕ʍ��u���̉f����ς�I�A�j�̃G���^�[�e�C�����g�W�O�O�{�v�Ɍf�ڂ���Ă���c���g�������̃��r���[�i�ނ͂��̉f�����{�̃|�C���g�E�u�����N�v�i���[}�[�r���剉�̐V���o�̎E�����f��j�����I�ƌ��������Ă܂��i���j�j�ɂ���悤�ɁA�P���E���b�Z������́A�ڂ��^���悤�ȃT�C�P�f���b�N���j���p�ȃx�b�h�V�[���ł���i���j�B
�e�����˂���Đ^���Ԃɐ��܂钱�X�A�x��p�v�A�j���[�M�j�A�̓y�l�A�lj�E�E�E�ȂǂȂǕs���ȉf�����U��߂��Ă䂭�̂ɂ̓N���N�������ςȂ��I�����čŌ�͔R���オ���āA�^���Ԃȑ��z���E�E�E�I���āA�Ƃɂ���������ῂ�����悤�ȃT�C�P�f���Ȃ̂ł���I�i�j�B
�����ċɂ߂��͉��ƌ����Ă��A�����������܂�ɑS�g�^�����ɓh���ēy�l�X�^�C���ň�S�s���Ƀ{���S��@���܂����叫�ƒ����Ԃ�U��Ȃ���x��܂����u���q�B
����ɂ͂������C�ɂƂ��邵������܂���B�͂����肢���ĂQ�l�Ƃ������̕ϑԁi�j�B
�S���Ӑ}�����߂Ȃ��I����ׂ��U�O�N��I������ׂ����{�I
���Ă��Ęb�̂ق��͂Ƃ���g�D�̎菕����������叫���G�̎E�����ɑ_����悤�ɂȂ�A��叫�̗��l�ƂȂ�����u���q���g�D�ɎE����A�̂Đg�̕��Q���J��L����Ƃ������P���Ȃ��̂Ȃ��ǂ��A����̐��b�l�Ɋݓc�X�A�G�̃{�X�ɏ���ȂǂȂǁA�ȎҐ������B
�u��X�ɕK�v�Ȃ͉̂Ȋw�ł͂Ȃ����C���[�W�A��_�ȃQ�o���g���v�Ȃ�Ă����܂�Ń��`���N�`���ȃx�b�h�V�[���̌�����݂����ȃi���[�V����������������Ă�����ρi�j�B
�Ƃɂ�����̃��u�V�[�������͐���P�x�E�E�E�j�����i�ݓc�X���ɁB�j�q���Ɂj�B
���Ȃ݂ɂ��̉f�悪��D���ȏ��c�D��́u�V�Y�V���[�Y�v�ւƒ��肷�邱�ƂɂȂ����B
���i���C��
|
|
�낢���ƂȂ�K�ɂȂ�
�ēF�����N
�r�{�F�R�蒉���E�r�c��N
�L���X�g�F���ˏ��A����_�V�A��u�����q�A����K��Y�A���g�S ������
�P�X�U�Q�N�i�����j
�������������X�A�����ǂ̎�������p�X�J�V����~�c�}�^�����҂��̎�ɂ���ċ��D���ꂽ�B��������K���X�̂Ђ�����������̋��ȃK���}���h�K���X�̃W���[�h�i���ˏ��j�A�u�T���ƍ߁v�̕ҏW���ʼn��ł����l�ɂ��Ĕ��f����h�v�Z�ځh�i����T�V�j�A�u���h�[�U�[�𑀂�r�����u�����i����K��Y�j�����͂��ꂼ��ɋA������U�D��萢�E��̍�{�V�l��߂炦�ĔƐl�ɍ�������t���悤�ƉH�c��`�ɏW�����邪�A�Ɛl�͂�������z���Ă��Ċ��ɍ�{�V�l���������ɘA�ꋎ���Ă����B�W���[���肪��������Ƃɂ��ǂ蒅�����M�����O�̎������ɂ����鏑�A�i���Z�D���̏��q�吶�E�Ƃ��q(��u�����q)�̓W���[�̂����ŃN�r�ɂȂ��Ă��܂��A���w��p���҂��׃W���[��Ɍ�����点�悤�ƁA��̂Q�l�Ƌ��ɃM�����O�Ƃ̘V�l���D��ɎQ���B�ʂ����ĘV�l�͂ǂ���̎�ɁH������Ƃ͖{���ɑK�ɂȂ�̂��H�E�E�E�ǂ����͊ςĂ̂��y���݁i�j�B
���X�ƎD���̕��U��f���̒��u���Ȃ����E���̂͒N�`���₽���i�C�t�Ŏh���̂͒N�`��v�Ƃ����a�`���u���[�X�^�b�`�̃e�[�}�������������Ƃ����I�[�v�j���O�Ƃ͗����ɁA���p���I�ȃW�F�b�g�R�[�X�^�[�I�ȓW�J����������e�ɂ�䩑R�ł���{��́A����}���R�̖��͑S�J�́u���j���̃��J�v�A�g�����t�H�[����^�̘a���k�[�x���o�[�O�u�������ʎ��v�A���_�����Ȃ܂߂������u���̏�̐A���Q�v�ȂǂȂǃ��_�������L����i���肪���������N�̏����̒ɉ��M�����O�A�N�V�����B
�r�{�͌�̋����p���A�V���p���̑�P�b���肪�����R�蒉���Ƃ����A�e���|�̂����W�J�╵�͋C���[���̃X�^�b�t�ł���i�j�B
���X�g�t�߂̖��ߗ��Ēn�ł̎������ł̃����O�V���b�g�ł͕ė��قǂɂȂ����l������������Ȗ��Œǂ��Ȃǂ̓˔�ȃA�C�f�A����т����܂��B���Ȃ݂Ƀ^�C�g���́u������ƂȂ�v�Ɠǂނ����ȁB
���i���C��
�@
|
�Ƒ��Q�[��
�r�{�E�ēF�X�c�F��
�L���X�g�F���c�D��A�ɒO�\�O�A�R�I������A�{���Y���A�ː쏃 etc.
1983�iATG�j
�������`�s�f�f��̌ւ�A�܂��ɒ�\�Z�f��̋������B
���y����؎g�킸�A�H�ׂ鉹�Ƃ����ʉ����C�������قǂɋ����B�������������Ƃ̂Ȃ��T�l������ō���H�삩�炵�Ĕ�������Ղ�ŁA�ݒ肩��Z���t���܂Ōv�Z���s������Ă܂��B
�����Ă��̉f��ɂ�����A��k���{�C�������ς����Ȃ��̃Z���t��}�g�Ȃ����\��łڂ��ڂ������₭�ƒ닳�t���̏��c�D�삪�ō��B�E��ɂ͐A���}�ӁA�����D�ł���Ă����̉ƒ닳�t�B��A�̃A�N�V�����f�擙�̃n�[�h�ȃC���[�W����ɔ�߂����̖�����͎��ɕs�C�����`���I���|�P�b�g�����44�}�O�i���ł͂Ȃ��A��⊾���ӂ����߂̃n���J�`���o�Ă����肵�āB
�▭�Ƀ{�[�b�Ƃ��Ă���R�I��������A�ڋʏĂ��̉��g���`���[�`���[������ɒO�\�O���A�r���Ń}���V�����̂ɂ����鎀�̏����ɂ��āH���k�ɂ���Ă���ː쏃�����Ȃ�L�Ă܂��B
�ǂ������������L�����N�^�[���������ݏo������"�c��"��"�Y��"�͈�x�n�}��Ɣ����o��܂���B �ŁA����ς茩���̓��X�g�t�߂̂V���ɋy�ԁu�Ō�̔ӎ`�v�B�ΔV�N�̍��i�j���ɂ����āA���H��ʊ�ŐH��������~���āA�Ƒ������������~�����~���āA�������ɂƂ����X��K�ڂɃR�[�g�݂̋�炵�Ȃ��狎���Ă������c�D��ɂ͈����B�������Ȃ��������̂悤�ɏt�����ނ��ڂ���c�Ƃ̃��X�g���s�C�����B
 �L�l�}�{��x�X�g�P�ʁA�ē܁A�剉�j�D��(���c�D��)�A�����j�D��(�ɒO�\�O)�ȂǁA84�N�̓��{�f��E�����|��������B�l�͂��̃Z���X���Q�̉f������������ɁA�M��Ƀn�}�邱�ƂɂȂ����B �L�l�}�{��x�X�g�P�ʁA�ē܁A�剉�j�D��(���c�D��)�A�����j�D��(�ɒO�\�O)�ȂǁA84�N�̓��{�f��E�����|��������B�l�͂��̃Z���X���Q�̉f������������ɁA�M��Ƀn�}�邱�ƂɂȂ����B
���i���C��
�@
|
�e�ۃ����i�[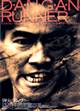
�r�{�E�ēF�T�u
�L���X�g�F�c���g�������ADIAMOND��YUKAI�A��^��A���Ԏ��A���ЂƂ�
������ �P�X�X�U�i�����j
������l���������ςȂ��̏�Ȃ��j�c���g�����������N�A��s���������݂邪�}�X�N���Ȃ��I�T�}�ɂȂ��H�I�����ăR���r�j�ɕ������q���p�̃}�X�N���������Ă��Ȃ��A�I�}�P�ɃW�����L�[�X���̃_�C�������h�����J�C�ɖ����������ꖜ���x���B���������ŏe��X���ɒD���ĕ����������i�[�c���g�������͑���o���̂ł������I
�ǂ��W�����L�[�X���A�����镉�����j�̐}�ɁA�g���̃^�e�ɂȂ�͂����h�q�̃h�X���悯�Ă��܂��đg�����E�����Ă��܂�����ɕ|���ăI�g�V�}�G�������Ȃ��ւ��ۂ����N�U�E�^�P�_�i��^��j���Ђ��Ȃ��Ƃ���Q���A�R�l�̒e�ۃ��[�X�������J����I�����ɑg���̓G�Ɨ����オ�郄�N�U�A�}�������N�U�A������������Ă܂Ƃ߂đߕ߂��悤�Ƃ���x�@������Ń��X�g�܂łЂ�����˂�����ɉ��ȂW�Q���B
���N�U�~�Q�g�ƌx�@�ƒe�ۃ����i�[�~�R���ꓯ�ɉ�܂ł̃X�������O�ȓW�J�����邱�ƂȂ���A�����Ă�r���ł���Ⴄ�L���`�u���D(���ЂƂ�)�Ƃ̎O�ҎO�l�̖ϑz�A�e�̏o�������炩�ɂȂ��Ă����l�q�ȂǁA�r���ő���R�l�͂������A���C�y�Ȍx�@�A������R���郄�N�U�A���܂ŁA���ꂼ��̃L�����N�^�[�ɃX�|�b�g�ĂĂ���������A�^�����e�B�[�m�I�ȕ��G�ȃv���b�g���I�݁B��b�̃Z���X���O�[�B
��Ȃ��𑶕��ɔ��������c���E�痼���ɂ�����B
�u���U�{�A�E�h�b�O�X�v��u���b�N�E�X�g�b�N�E�g�D�[�E�X���[�L���o�����Y�v�����肪���C�ɓ���̐l�ɂ͌��I�X�X���B
�Ƃ���ŏ��c�D��̈�e�ɂ���Ђ�����Y���ƔƐl������u�h�b�O�E���[�X�v���ߔN�×z��ēɂ���āu���A����v�Ƃ��ĉf�扻���ꂽ���C�}�C�`������Ȃ������ł������B������̂ق����A���c�D�삪��肽�������C���[�W�ɒf�R�߂��悤�Ɏv����B
���Ȃ݂ɑ�����Q��u�|�X�g�}���E�u���[�X�v������B���x�͒炳��A���]�Ԃœ˂�����܂��i�j�B
���i���C��
|
|
���Ƃ₩�ȏb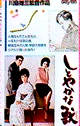
�r�{�E�ēF�쓇�Y�O
�L���X�g�F�ɓ��Y�V���A�R���v�T�A������q�A�D�z�p�� etc.
�P�X�U�Q�i��f�j
����������璆�N�v�w�����������ƉƋ���ړ������Ă���x�����_�̌������̕������C�ɂȂ�I�[�v�j���O�B�����Ń��I�I�I�I�I�I�b�I�Ƃ����Ȃ�苿���\�̂����q���o�b�`���ƌ��܂�B���͂��̕v�w�i�ɓ��Y�V�����R���v�T�j�A�͌|�\�v���_�N�V�����ɋ߂鑧�q�ɉ�Ђ̋����g�����܂��A���𗬍s��Ƃ̂Q���Ƃ��čv�����Ă���Ƃ����S���O���̂Ƃ�ł��Ȃ��K�Q�o�Ƒ��ŁA�����̒��������ґ�ȕ�炵�i���Ă����̂������I�i�j�B
���̓��A���q�̎g�����݂��o���ăv���_�N�V�����̐l�ԒB����荞��ł���̂ŁA���������n�R�Ƒ��ɕϐg�A����ō����ȊG���Ƌ����ЂÂ��A��������f�ȕ����ɒ��ւ��Ă����̂ł���i�j�B
���̌�A��̗��s��ƁA�����čő�̋��G�A������q������|�\�v���_�N�V�����̂����������l�ٌ�m�i����{���ɂ��������Ŕ������E�E�E�j��A�O������̖K��ɂ���ď��X�ɔޓ����z���Ă����T���N�`���A�������Ă������A�S�����肽�l�q�͂Ȃ��W�X�Ɖf��͐i��ł䂫�܂��B
����ɂ��Ă��A�قƂ�ǂ��̃A�p�[�g�̈ꎺ�����œW�J���Ă䂭�̂����A��ɒN�����B��Ă���A���C���̂����ȂǑ��p�x����U�߂�Ђ˂��ꂽ�J�������[�N�̃Z���X�͖M��j��i���o�[�����ł͂Ȃ��낤���H���X�ƖK��Ă����ȗ��K�҂����Ƃ̋삯�������▭�ŁA���̉�b�̃e���|�����Q�����A�����ɐD�荞�܂ꂽ�A���I�ȊK�i�ƒʘH�𑖂蔲�����ȐS���`�ʂ���������ۓI�����ʓI���B
�����Ċ����Ɏ���Еt�����͂��̔��l�ٌ�m�E������������A1�l�̒j�̍s�����^����ς��Ă��܂��E�E�E�B���X�g�A�J�̒������n�邨���q�ƎR���v�T�̗��₩�ȕ\���ۓI�B
�u�������z�`�v�ŗL���ȋS�ː쓇�Y�O�ḗu�K���S�āv�̓��{�l�̃Z�R�Z�R��������Љ��1962�N�ɂ��Ēɗ�ɕ��h���Ă݂����A���ߑ����u�t�n�[�v�ƘR���قǂ̃u���b�N�Ȋ쌀�̌���B
�����Y��Ă������A���ꉉ����ӎU�L���V�����\���̎�A�����Łu����Ȃ����炨������ɂ������������[�v�Ƃ܂��߂Ȋ�Ŕ���ɓ��Y�V�������镃�e�͔��I���ꂾ����M��͂�߂��Ȃ��I�I�I
���i���C��

|
�S�W��VS�w�h��
�ēF���`��
�L���X�g�F�S�W���A�w�h���A�R�����A�ؑ��r�b�A�쐣�T�V etc.
�P�X�V�P(����)
����������A�R�o���g�A�J�h�~�E���`�A�}���K���A�I�L�V�_���`��Ƃ�����V��ȃe�[�}�\���O�L���ȃJ���g�M��̋������I��i�́A��̏������T�C�P�f���b�N�Ȕw�i��w�ɉ̂��I�[�v�j���O�A�`���[�~���O�ȃA�j���摜�A�q���̔M�����b�Z�[�W���悹���앶�A����ɂ̓j���[�X�⌟�ؔԑg�܂Ńt���[�`���[���ꂽ�����Ƃ��ُ�Ŋ�V��ȃS�W���f��ł���B
�l�Ԃ̗����������琶�܂ꂽ�w�h���͋}���ɐi�����J��Ԃ��A���_����܂��Ȃ����s����悤�ɂȂ�A���l���o�B��͔r�C�K�X�ɕ����A�������Ȃ��Ă䂭�B
�����Ă���ȏ������˂��̂��A�w�h����|�����߁A�[�Ă����o�b�N�ɃS�W�����o�ꂷ��̂ł������E�E�E�I
�܂��͂����肢���ăS�W���ƃw�h�������Ⴀ���Ⴀ�����Ȃ��瓬���Ă�V�[���Ȃ͓��B�ɑa�������ɂ͑ދ��ł͂���̂����i���j�A���ƌ����Ă������ɎU��߂�ꂽ���T�C�P�ȉ�ʂ���60�N��̓��{�̃q�b�s�[�������w�ׂ�̂��O�[�Ȃ̂��i�j�B
�u�������̐S�̒��ɂ��������͂˂��A�݂�ȗx�낤���I�v�Ɣ����P�N�\�ŊJ�Â������Q���Ή^���Ȃ�ʌ��Q���S�[�S�[�Ȃ�_���X�W��A���łɃ������Ă��܂��N�A�{�f�B�y�C���e�B���O�̃C�P�C�P�Ȃ��o���x��Ȃ���̂���̃e�[�}�\���O�B���̂ւ��ƌ����Ă������ł͂Ȃ����낤���H�i�j
����Ȉُ�ȃe���V�����̒��A���݂ɋ���т܂��A���݂Ɍ`��ς���w�h���ɕИr������ȂǑ��킷���炪�S�W���B���{�̉^���₢���ɁE�E�E�H�����Č��Q���S�[�S�[�͂ނ�����̂��H�i�j
���A���I���Ԃ��I���̒��T�C�P���t�����[���n�b�s�[���I�M���I�I�I�X�I�i��j
���i���C�� �@
�w�S�W��VS�w�h���x�e�[�}�\���O
�������������֍s�����̂��`�H
��x�����������֍s�����̂��`�H
����I�R�o���g�I�J�h�~�E���I ���I���_�I�I�L�V�_���I
�V�A���I�}���K���I�}�i�W���[���I �N�����I�J���E���I�X�g�����`���[���I
���ꂿ�܂����C ���ꂿ�܂����� �������݂�ȁA���ȁ[���ȁ[���� ����R���ق����܂����`
�n���̏�ɒN���`�N�����Ȃ���ዃ�������`�ł��Ȃ��`
�Ԃ��`�I�i�Ԃ��`�I�j �Ԃ��`�I�i�Ԃ��`�I�j ���`����`�Ԃ��`�I �Ԃ��`�I�i�Ԃ��`�I�j ���C��Ԃ��I�Ԃ��`�I�i�Ԃ��I�Ԃ��I�j �Ԃ��`�I�i�Ԃ��`�I�j
�Ԃ��`�I�i�Ԃ��`�I�j ���z��Ԃ��`�I�Ԃ��I�i�Ԃ��I�Ԃ��I�j �Ԃ��I�Ԃ��I�Ԃ��I ���`���`���`�I�I�I�@
|
�q�|�N���e�X����
�r�{�E�ēF��X���
�L���X�g�F�Ô��J��l�A�ɓ����A���{���A���q��Y�A���c���O�A�n�ӕ��Y�A���ׁA�^��u�����q�A�����C�A�֓��m��A��ˎ����A���c�F�Y�A��ؐ����A�X�{���Ietc
�P�X�W�O�i�V�l�}�n�E�g�{�`�s�f�j
��������X����������̌o�������Ƃɕ`������i�ŁA������҂�u���b�N�Ŋ��m�Ń��A���Ȑt�f��B
�����g���A���ɖ��������吶�����̍Ō�̂P�N�B�����܂ŗ��Ă܂���҂ɂȂ邩�ǂ����Y�ݑ�����A
����������Ȃ�����i�Ô��J��l�j�A�q�����w���̔N���҉����i���{���j�A��҂ɂȂ邱�Ƃ�Y�ނ݂ǂ�i�ɓ����j�A�K���׃^�C�v�̑哇�i���ׁj�A�싅���N������̉��i���˔��j��U�N���̓|���E�N���ƌĂ��Տ����K�̖����𑗂��Ă����B
�܂��A����̏Z�ރI���{�����h�ɂ͐��_���ڎw�������i���q��Y�j�A�V�����h�w���̓�c�i�������u�j�A �������W�N�ڂ̖{�c�i�֓��m��j�ȂLj�Ȃ���Ȃ�����A�����Z�݁A��������ɔY�݁A���܂�����A���Ȃ��畨��͐i��ł����B
����ɂ���D�@�̎������p�X�������A����͗��l��D�P�����Ă��܂��A��������������ȎY�w�l�Ȃł��낷�̂����A���̂��e�̂��������Ĕޏ��͎��Ƃɖ߂邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
����͌��߂��������������Ȃ�������Ƃ��߂Â��A���Ǝ����Ɍ����ĕ������n�߂����ޏ����݂�����҂����u��҂œE�����ꂽ�j���[�X�����A����͌���I�ɐ��_�̃o�����X������Ă��܂��A���犳�҂ƂȂ�A���_�Ȃɓ��@���邱�ƂɁE�E�E�B
��������������L���ȃL�����N�^�[�ɉ����A�����Ȃ̐搶�ɂ͎�ˎ����A��p����Ƀ^�o�R���K���K���z���Ȃ��牬�삽�����������i�j���c�F�Y�A�R�\�D���̗�ؐ����A���Ǝʐ^���B�e����J�����}���ɐX�{���I�Ȃlj��Ƃ����ȃQ�X�g�w�������œo�ꂵ�A�y���܂��Ă����B
����ɂ͉f�拶�̗������{�̕����ɂ́u�^�N�V�[�E�h���C�o�[�v��u�C�����s�G���v�̃|�X�^�[�A�u����ɂ��₪��v�̃W�[���E�Z�o�[�O���ۂ��^�o�R���z������̗��l�A�u12�l�̓{���j�v�̃Z���t�̈��p�A�̎B�����W�~���f��̓o��ȂǁA�f��D���̑�X�ē炵���t�ւ̃I�}�[�W���Ɉ��Ă���B�����������Ӗ��ł��܂��y���߂��i�B
�ǂ��t�f��̓m�X�^���W�B�ƃ��A���ւ̋����A�����ĉ����u���̍��ɖ߂肽���v�I�~����������̂ł���B���̉f��͏\�ɂ����̃R���e���c�����Ă��Ăǂ��������������犴����B
�l��͂ǂ��ƂȂ���Ȃ����숤��ɋ������A�ޓ��ɂ�����艟�����錻�����������A�����g���A���ȋ�C�ɋ��D�������邱�Ƃ��ł���B
��X�ē̏���̒��ł��Y�o�������ǎ��̐t�f��i�̃n�Y�j�ŁA�P�X�W�O�N�x�L�l�}�{����{�f�敔��R�ʂ̖���B
���i���C��
|
| �@ |
�@ |
�@ |
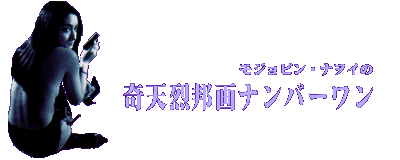
![]()
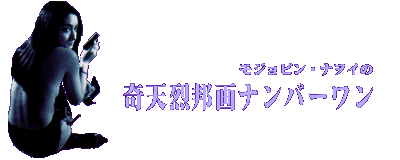
![]()